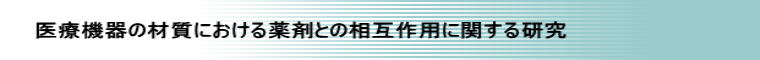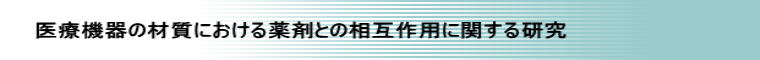|
|
| 研究概要 |
背景と目的
医薬品投与に用いられるプラスチック製医療機器が併用する薬剤の影響により破損する事例が報告されている。これらの医療機器に用いられる材料は様々である。また、医薬品には、薬剤成分に加え、pH調整剤、脂肪乳剤、界面活性剤等の添加剤が含まれている。医療機器の使用にあたっては、消毒用アルコール類と併用されることもあることから、医療機器と医薬品成分の組み合わせは多種多様となる。同種の医療機器であっても材質が異なること等から、安全対策の水平展開が一概に容易ではなく、現状では特定の組み合わせにおける注意喚起にとどまっており、その他の液性と材質間の相互作用については未知な部分が多い。
これらの事例の発生は医薬品及び医療機器メーカにおける検証と医療現場における管理体制が不十分であることに由来する。そこで本研究では、第一の目標として、業界団体と連携の下に医薬品と医療機器の相互作用が発生する可能性のある組み合わせの特定を試みた。また、第二の目標として、規制当局、関連学会等と連携の下、臨床現場の観点から行うべき情報提供の在り方のほか、医療現場における不適切使用の解消に向けて、医療関係者が留意すべき事項について取りまとめた。本研究で得られた成果は、規制当局の判断の下、必要に応じて厚生労働省通知の発出等を介して、医薬品及び医療機器業界に自主点検・検証を促すことにより、添付文書の改訂や製品改良に繋がると共に、医療機関における不適切使用の解消へ向けた取り組みの実施に資することが期待される。
研究体制と概要
(1)ハザード解析グループ(国立衛研)
曲げ浸漬試験及び引張浸漬試験により、各種プラスチック材料と疑似溶液の全ての組み合わせについて、ハザード解析が完了し、不具合が発生する組み合わせ及び濃度閾値を特定した。また、細胞毒性を指標として評価した結果、いずれの組み合わせでも相互作用の発生に伴う新たな毒性の発現は認められなかった。
PC又はPET製部材を有する実製品を用いた検証試験も全て完了した。宮城県立こども病院で発生した特定製品とフローランの組み合わせによる不具合は、実製品を利用した検証試験により再現できた。また、その他の製品を用いた検証試験では、相互作用により破損する製品が散見された。従来報告されていない新たな知見として、PETはPCと比較して、アルカリ性、消毒用アルコール、脂肪乳剤、界面活性剤に対する耐久性が劣り、これらの液性又は添加剤との組み合わせにより相互作用が発生することが明らかとなった。
フローランとの相互作用によりはっせいした特定製品の不具合発生は各部品の接着に伴う残留応力の存在が原因であると推察された。同じ材質から構成される製品でも、薬剤に対する耐久性が異なるものが存在する。環境応力割れが発生する原因としては、残留応力の存在の有無のほか、分子量、製造方法等が挙げられるが、製品の応力状態は四塩化炭素処理により検証可能であった。また、適切な条件でアニーリング処理を施すことにより、製造時の残留応力を除去できることも判明した。
3年間の研究成果を相互作用に起因する不具合やヒヤリ・ハット事例の発生回避に繋げるため、行政、並びに医薬品及び医療機器の製造販売業者へ向けた提言を取りまとめた。
従来、相互作用の発生に係る行政対応は特定の組み合わせにおける注意喚起にとどまっていたが、本研究において、相互作用が発生する組み合わせの全貌が明らかになった。また、相互作用の発生原因及びその回避策も解明した。これらの成果は、医薬品・医療機器メーカにおける自主点検、添付文書改訂、製品改良等への取り組みを促し、適正使用の確保、より安全な製品の供給等に資する施策へ繋がることが期待される。
(2)調査研究グループ(東北大学)
添付文書検索の結果、相互作用の発生について注意喚起されておらず、改訂が必要と考えられる製品が存在した。宮城県内及び全国調査の結果、臨床現場では様々な組み合わせで相互作用が発生していると共に、医療機器添付文書管理体制、情報共有システム、各責任者間の連携体制が確立されていない等、現状の問題点が浮き彫りとなった。また、新たな相互作用事例を把握するため、医療の質・安全学会、医薬品・医療機器団体及び医療機関等と連携の下、各種調査を継続して実施した。
本調査研究を通じて、医療現場における不適切使用を防止するためには、1)医療機器の適正使用に関する情報管理体制の構築、2)医療機器の材質や医薬品に含まれる添加物等の情報管理、3)医療機器の専門知識を有する人材の育成、4)医療機器安全管理責任者、医療安全管理者及び医薬品安全管理責任者の連携、5)薬剤と医療機器の相互作用に特化した研修、6)医療機関からの相互作用事例報告の推進、7)薬剤と医療機器の相互作用に関する事例データベースの整備、8)医療機関、製造販売業者及び行政間の情報共有の強化等に関する取り組みを行うことが重要であることが判明した。
これらの知見に基づき、調査研究グループでは、不適切使用の解消へ向けた対策として「臨床現場の観点から行うべき情報提供の在り方と医療関係者が留意すべき事項に関する提言」を取りまとめた。また、医療機関へ配信する方法について規制当局を含む産官学メンバー全体で検討した。
本研究で取りまとめる提言は、医薬品・医療機器の適正使用を確保し、相互作用に由来する不具合やハヤリハット事例の削減に寄与できることが期待される。 |
|
|
|